猫 避妊 手術 後 発情 期 — このフレーズには多くの飼い主が驚きや戸惑いを感じるでしょう。避妊手術を受けたにも関わらず、なぜ発情期が訪れるのか、その理由や対策について詳しく見ていきます。
猫の避妊手術について知っておくべきこと
避妊手術は、飼い猫に対して行われる一般的な医療処置です。これは主に、望まれない妊娠を防ぎ、発情行動を抑えることを目的としています。通常、手術後は発情期の行動が見られなくなるはずですが、一部の猫では手術後にも発情期が訪れることがあります。
ここで、避妊手術の一般的な流れと期待される結果をまとめた表をご覧ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手術の目的 | 望まない妊娠を防止 |
| 手術方法 | 卵巣と子宮を摘出 |
| 手術後の期待 | 発情行動の消失、健康リスクの低減 |
| 回復期間 | 数日から数週間 |
| 手術の費用 | 地域や病院によるが、一般的には3万~10万円 |
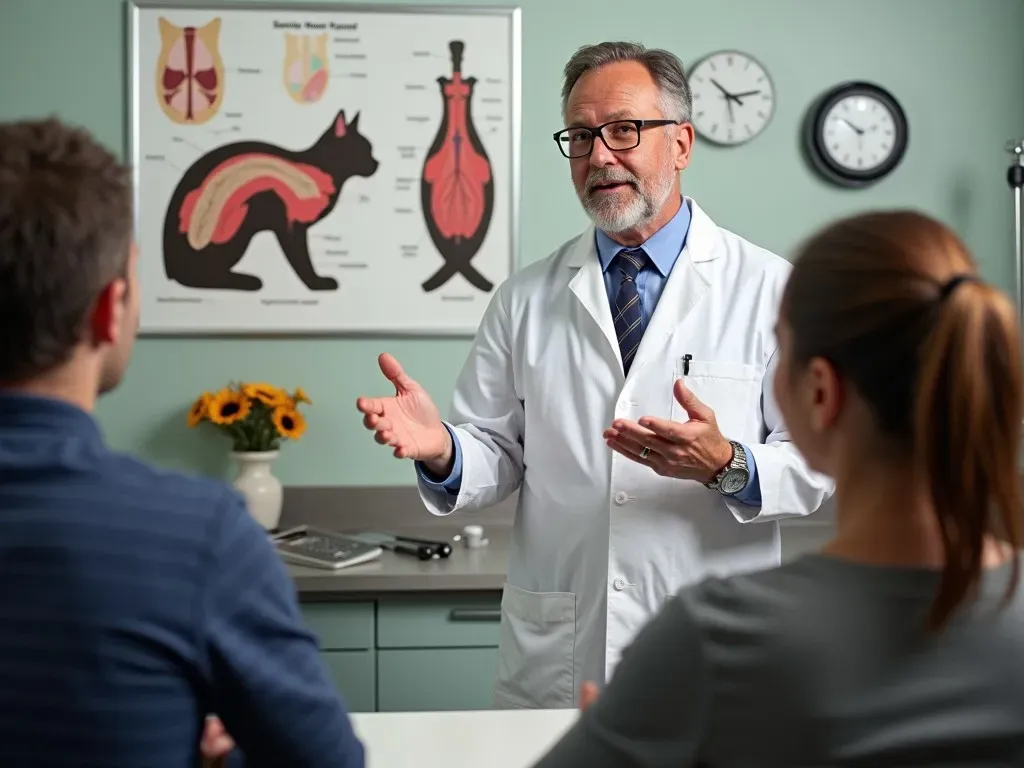
猫の発情期とは?
猫の発情期は、通常は春から夏にかけて発生します。この期間中、猫は繁殖行動を促進し、他の猫との交尾を求めるようになります。この行動は、オス猫だけでなくメス猫にも影響を与えます。
発情期の症状
- 大きな声での鳴き声
- 激しいスリスリ行動
- 対象物に対するマーキング行動
- 食欲の変化
これらの症状は、特に発情期の間に顕著になります。

手術後に発情期が訪れる理由
避妊手術後に発情が見られるケースにはいくつかの理由があります。ここでは主要な原因をいくつか紹介しましょう。
1. 卵巣遺残症候群
避妊手術が不完全であった場合、卵巣の一部が残ることがあります。この状態を「卵巣遺残症候群」と呼び、再び発情期が現れることがあります。症状としては、発情期の兆候が見られ、繁殖行動が再発します。
2. ホルモンバランスの変化
手術後はホルモンバランスが大きく変化します。このホルモンの影響で、一時的に発情期の行動が見られることがあります。特に、ホルモンの変化が大きい場合や、ストレスや刺激がある環境下では、発情行動が見られることがあります。
3. 環境要因
猫は環境に敏感な動物です。ストレスや変化に敏感で、他の猫の存在や季節の変化により発情行動が再発することがあります。
4. 実際の手術ミス
手術が成功したと思われる場合でも、稀に発情行動が見られることがあります。これは手術中のミスではなく、猫それぞれの体質に依存している場合があります。獣医師に相談することで、何らかの対処法を見つけることができるでしょう。
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 卵巣遺残症候群 | 手術後に卵巣の一部が残り、発情行動を引き起こす |
| ホルモンバランス | ホルモンの変化による一時的な発情行動 |
| 環境要因 | ストレスや他の猫の存在により発情行動が再発する |
| 手術ミス | 手術中の不完全さが影響している場合がある |

参考動画
発情期に対する対処法
猫が避妊手術を受けたにも関わらず発情行動を示す場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
1. 獣医師に相談
まずは、獣医師に相談することが基本です。発情行動を観察したら、すぐに相談し、適切なアドバイスを受けましょう。
2. 環境の改善
猫は環境に敏感ですので、ストレスを軽減するためには静かな環境を作ることが重要です。また、他の動物との接触を控えることも役立ちます。
3. ホルモン療法
獣医師によっては、ホルモン療法を提案することがあります。これにより、ホルモンバランスを安定させ、発情行動を抑えることが期待されます。


